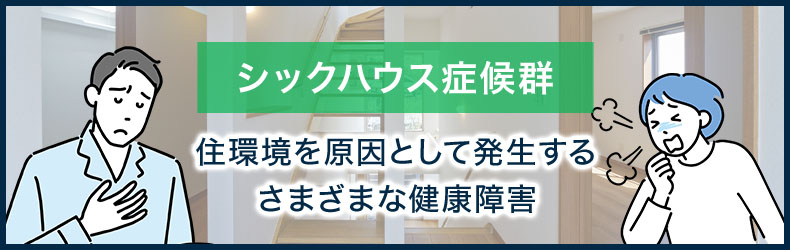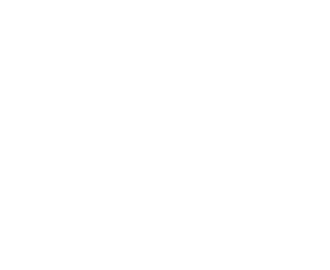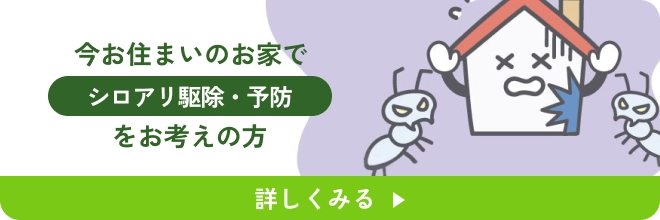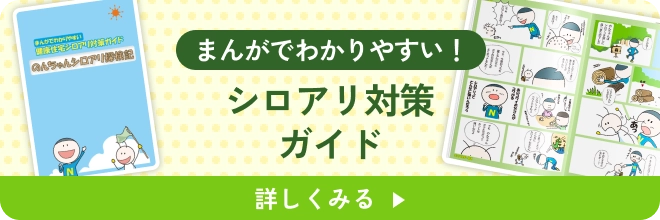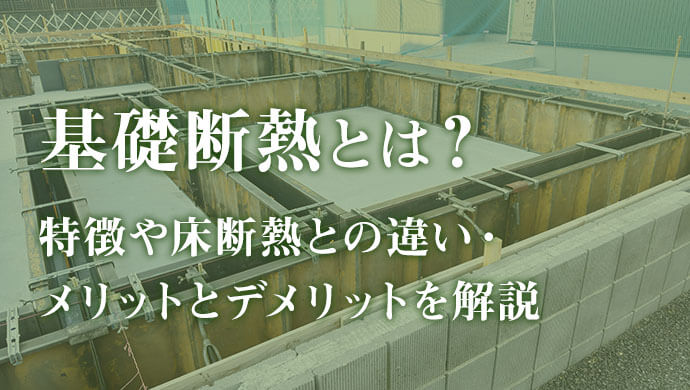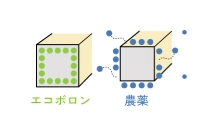新築はシックハウス症候群になりやすい?主な症状や原因・対策を解説
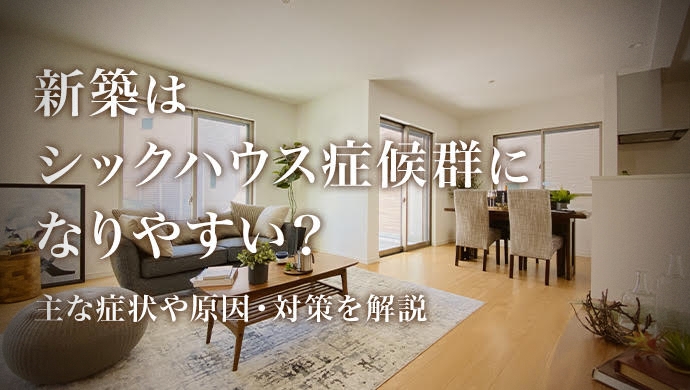
シックハウス症候群とは、住宅や建材から放散される化学物質やカビ、ダニなどが原因となって起こる健康被害のことです。目のかゆみや鼻詰まり、頭痛、さらには集中力の低下など、さまざまな症状が現れるのが特徴です。
当記事では、シックハウス症候群の原因や症状、新築の設計時・新築した後にできる効果的な対策について詳しく解説します。新築住宅に住む予定の方や、現在の住環境に不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。
シックハウス症候群とは
シックハウス症候群とは、住環境を原因として発生するさまざまな健康障害のことです。シックハウス症候群になった場合は住まいそのものに原因があるため、日常的に症状が現れる可能性があります。
原因がある建物から離れると症状が軽くなる点もシックハウス症候群の特徴です。
新築の家はシックハウス症候群になりやすい?
「新築の家はシックハウス症候群になりやすい」「シックハウス症候群は新築の家に多い」などの言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。しかし、シックハウス症候群になりやすいのは新しい建材や設備がある状態だからであり、新築の家だけがシックハウス症候群になりやすいわけではありません。
新築の家に限らず、リフォーム後や壁紙や床材を張り替えたとき、家具を購入したときなどのタイミングでもシックハウス症候群のリスクがあります。このようなタイミングでは建材などに使用されている化学物質が揮発・放散しやすく、化学物質を原因とするシックハウス症候群の発生につながります。
高気密な住宅では揮発・放散した化学物質が住宅内に滞留しやすいことも、新築の家がシックハウス症候群になりやすい一因でしょう。
1970年代以降、日本では住宅の結露対策として「通気層工法」や「防湿気密層の連続」といったアイデアが考案され、住宅の気密性が徐々に向上していきました。1999年に断熱基準が改正され、気密工事が明示されたことで現在の高気密・高断熱な住宅に至っています。
さらに、2003年7月に改正建築基準法が施行され、シックハウス症候群対策として新築物件には24時間換気システムの設置が義務付けられました。現在では、ガイドラインや建築関係の法制度が整備され、住環境中の化学物質の濃度は全国的に低下してきています。
シックハウス症候群の症状
シックハウス症候群の症状は個人差があり、症状が現れる部位にも違いがあります。
主なシックハウス症候群の症状は、下記の通りです。
・目
目のかゆみや熱さ、チクチクするといった症状が見られます。コンタクトレンズを装着している方は症状がより過敏に現れる可能性があるため注意してください。
・鼻
鼻の症状では鼻詰まりが最も多く、他にも鼻水が止まらなかったり、鼻がムズムズしたりする症状があります。
・皮膚
皮膚の症状としては顔・手・耳の乾燥や赤みがあり、かゆさを感じることもあります。特に女性の方は皮膚の症状が現れやすい傾向です。
・のど、呼吸器
声がかすれたり、喉が乾燥したりする症状が現れます。咳が出る、深呼吸ができないといった特に体調不良を感じられる症状もあります。
・精神、神経
精神や神経にかかわるものでは、頭痛の訴えが最も現れやすい症状です。頭痛とともに疲れやすさや倦怠感、集中力の欠如や不快感をおぼえたり、吐き気・嘔吐といった症状が現れたりするケースもあります。
出典:厚生労働省「科学的根拠に基づくシックハウス症候群に関する相談マニュアル(改訂新版)」
アトピー性皮膚炎や花粉症といったアレルギー性疾患の既往歴がある方は、シックハウス症候群の症状が現れやすいと言われています。
シックハウス症候群の原因
シックハウス症候群の原因は複数あり、対策するには原因を詳しく知る必要があります。
ここからは、主な原因として「化学物質」「カビ・ダニ・細菌」「住宅の構造」を挙げて、それぞれがどのようにシックハウス症候群を引き起こすかを解説します。
化学物質
木材・壁紙の接着剤や防腐剤、防虫剤などの用途で、住宅にはさまざまな化学物質が使われています。化学物質が徐々に揮発・放散して屋内の空気を汚染し、呼吸などで人体に吸収されることがシックハウス症候群の要因です。
特に揮発しやすい化学物質はVOC(揮発性有機化合物)と呼ばれ、シックハウス症候群の主要な原因物質とされています。
厚生労働省は下記の13種類の化学物質について、使用に際して室内濃度の指針を発表しています。
化学物質の室内濃度の指針値(厚生労働省)
| 化学物質 | 指針値※ | 主な用途 | |
|---|---|---|---|
| 厚 生 労 働 省 が 濃 度 指 針 値 を 定 め た 13 物 質 | ①ホルムアルデヒド | 0.08ppm |
|
| ②アセトアルデヒド | 0.03ppm | ホルムアルデヒド同様一部の接着剤、防腐剤等 | |
| ③トルエン | 0.07ppm | 内装材等の施工用接着剤、塗料等 | |
| ④キシレン | 0.20ppm | 内装材等の施工用接着剤、塗料等 | |
| ⑤エチルベンゼン | 0.88ppm | 内装材等の施工用接着剤、塗料等 | |
| ⑥スチレン | 0.05ppm | ポリスチレン樹脂等を使用した断熱材等 | |
| ⑦パラジクロロベンゼン | 0.04ppm | 衣類の防虫剤、トイレの芳香剤等 | |
| ⑧テトラデカン | 0.04ppm | 灯油、塗料等の溶剤 | |
| ⑨クロルピリホス | 0.07ppb (小児の場合0.007ppb) | しろあり駆除剤 | |
| ⑩フェノブカルブ | 3.8ppb | しろあり駆除剤 | |
| ⑪ダイアジノン | 0.02ppb | 殺虫剤 | |
| ⑫フタル酸ジ-n-ブチル | 0.02ppm | 塗料、接着剤等の可塑剤 | |
| ⑬フタル酸ジ-2- エチルヘキシル | 7.6ppb | 壁紙、床材等の可塑剤 | |
※25℃の場合 ppm:100万分の1の濃度、ppb:10億分の1の濃度
①⑨は建築基準法の規制対象物質
①~⑥は住宅性能表示で濃度を測定できる6物質
引用:国土交通省「改正建築基準法に基づくシックハウス対策」引用日2024/05/14
カビ・ダニ・細菌
カビ・ダニ・細菌はアレルギー症状を引き起こし、シックハウス症候群の発症や症状悪化につながる可能性があります。住宅内は湿度や温度が高く保たれるため、カビ・細菌が繁殖しやすい環境です。カビ・細菌はアレルギー症状によるシックハウス症候群だけでなく、感染症を引き起こす可能性もあります。
また、ダニの糞や死骸はアレルギーの原因物質です。住宅内が高温高湿度の状態になっていたり、ペットを飼っていたりする方はダニの発生に注意しましょう。
住宅の構造
高気密化を目的とした住宅の構造が普及したことも、シックハウス症候群の原因として挙げられます。
昔ながらの日本の住宅は、夏季の高温多湿への対策として隙間や大きな開口部を設けるなど、空気が流れやすい構造をしていました。気密性が低く、結果としてシックハウス症候群を防ぐことができたと言えます。
しかし、1970年代以降、日本の住宅は気密性が徐々に向上してきたため、空気が流れにくく化学物質によるシックハウス症候群のリスクがあると言われていました。そこで2003年に「シックハウス対策のための規制導入 改正建築基準法」が施行されました。
出典:国土交通省住宅局「シックハウス対策について知っておこう」
建築基準法改正により、「住宅の居室では0.5回/h以上の機械換気設備(24時間換気システム)の設置が義務付けられ、シックハウス症候群に関する相談件数も徐々に減少しています。
ただし、住宅の気密性が高いと湿気が溜まりやすくなり、カビやダニが発生する原因になります。カビやダニがシックハウス症候群を引き起こすきっかけになることもあるので注意が必要です。
新築でのシックハウス症候群を抑えるための対策
シックハウス症候群は対策することで症状の発生や深刻化を抑えられます。
以下ではシックハウス症候群の対策方法を、「新築の設計時」「新築を建てた後」の2つに分けて紹介します。
新築の設計時にできる対策
新築の設計時にできる対策としては、下記の方法があります。
- 化学物質が含まれる建材の使用や内装を控える
- 接着剤を減らした設計にする
- 換気が十分にできる間取りにする
特に建材は「F☆☆☆☆(エフ フォースター)」のマークを見て選びましょう。F☆☆☆☆はJIS(日本産業規格)やJAS(日本農林規格)が定めたホルムアルデヒド発散等級の1つで、ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ないことを示します。他にも、内装材や造作家具の材料に無垢材を使って接着剤を減らすという工夫もできます。
また、高気密・高断熱住宅では湿気が室内に溜まりやすく、シックハウスの原因となるダニやカビが発生しやすくなる点に注意が必要です。換気を十分に行える間取りに設計することで、湿気や暖房器具から出る一酸化炭素なども排出しやすくなるでしょう。
さらに、気密性・断熱性が高い住宅は、場合によっては基礎部分の断熱材にシロアリが入り込むケースもあります。気密性・断熱性が高い新築住宅をシロアリ被害から守るには、防蟻剤でシロアリ対策をすることが重要です。
前述の通り、建材にはシックハウス症候群対策としてホルムアルデヒドの発散量を基準としたF☆☆☆☆が定められています。F☆☆☆☆が表示されている建材を使うことで安全性が高くなりますが、防蟻処理剤は建築基準法の指定製品ではないためF☆☆☆☆などの表示がない点に注意しましょう。
建築基準法では、地面(GL)から1メートル以内の防蟻処理が必須とされており、この範囲に使用される柱などの外壁軸組材も対象となります。そのため、防蟻剤の成分が室内空気に影響を及ぼす可能性がある点にも注意が必要です。防蟻剤を選ぶ際は、成分表示をしっかり確認し、安全性に配慮した製品を選びましょう。
たとえば農薬系の防蟻剤は揮発しやすく、室内空気中に成分が拡散することで、人体に悪影響を及ぼす可能性があります。一方、ホウ酸系の防蟻剤は揮発せず、成分が空気中に漏れ出さないため、安心して使用できます。また、ホウ酸は自然由来の素材であり、シックハウス症候群のリスクを心配する必要がありません。このため、健康面や安全性を重視する場合には、ホウ酸系の防蟻剤がおすすめです。
エコパウダーでは、お子様の健康に配慮された商品として、キッズデザイン賞を受賞し、赤ちゃんや妊婦さん、アレルギー体質の方まで安心して使えるホウ素系防腐防蟻剤「エコボロンシリーズ」を取り扱っています。カビに抵抗性があり細菌類にも効果があるので、新築のシロアリ対策として安全に配慮された防蟻剤をお探しの方は、ぜひ下記の商品詳細をご覧ください。
新築を建てた後にできる対策
新築を建てた後やリフォーム後は、いくつかの対策を実践してシックハウス症候群を抑えましょう。新築やリフォーム直後は、室内の化学物質が多く発散されるため、しばらくの間は十分な換気や通風を心がけてください。
また、換気設備はフィルターの清掃など、定期的なメンテナンスを行うことも大切です。24時間換気システムは、スイッチを切らずに常に稼働させましょう。
洗剤・消臭剤・芳香剤や化粧品、タバコなども化学物質の発生源になり得ます。入居後にシックハウス症候群の症状が現れたときは、化学物質を可能な限り減らして生活することが大切です。
まとめ
シックハウス症候群は、住宅内の空気汚染によって引き起こされる健康被害のことを指します。化学物質やカビ・ダニが原因となり、目や鼻、皮膚に現れる症状だけでなく、頭痛や倦怠感など全身に影響を及ぼすケースもあります。特に新築住宅やリフォーム直後の住環境では、建材や接着剤から揮発する化学物質の影響が大きいとされています。
シックハウス症候群を防ぐためには、新築の設計時に環境に優しい建材の選択や接着剤を減らした設計にすることが有効です。また、防蟻剤についても注意が必要です。従来の農薬系防蟻剤は揮発性が高く、人体への影響が懸念されますが、ホウ酸系防蟻剤は揮発せず、空気を汚染しないため、安全に使用できます。さらにホウ酸は自然由来の素材であり、シックハウス症候群のリスクを軽減します。
エコパウダーの「エコボロンシリーズ」は、赤ちゃんや妊婦、アレルギー体質の方にも安心して使えるホウ素系防腐防蟻剤です。シロアリ対策だけでなくカビや細菌にも効果を持つため、新築住宅を建てられる方にもおすすめです。健康と安全を重視したい方は、ぜひ商品の詳細をご確認ください。